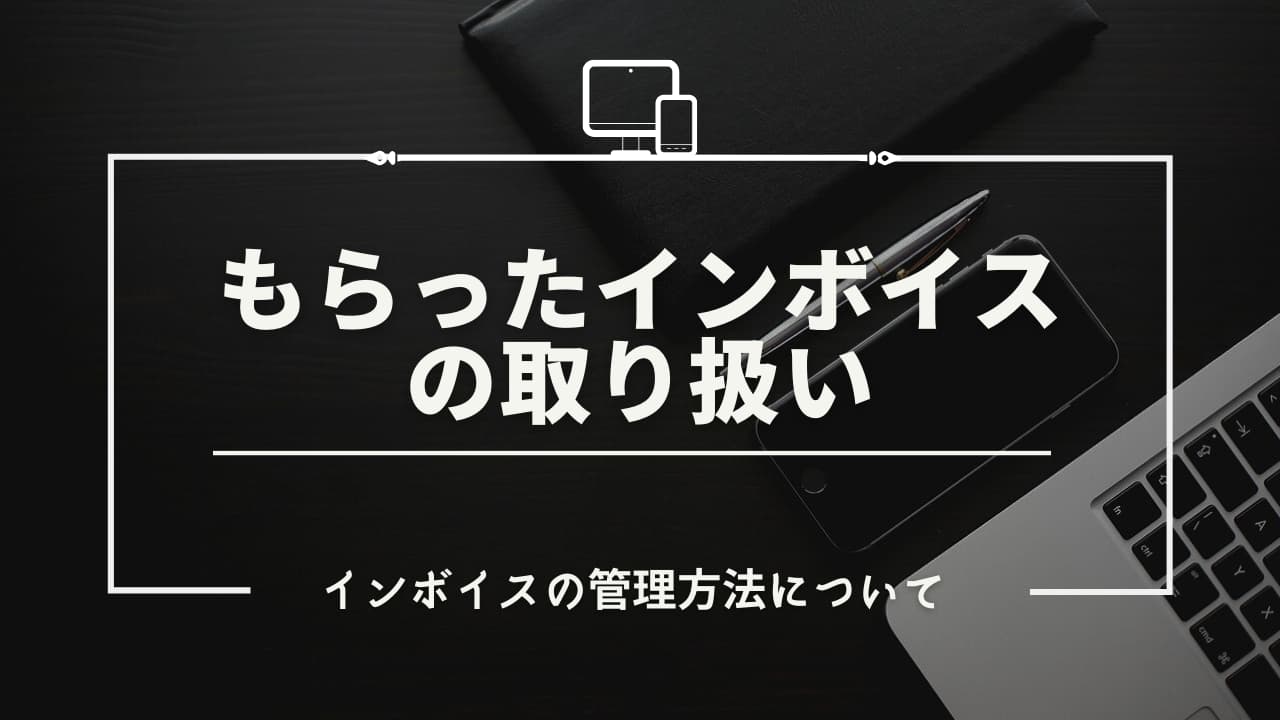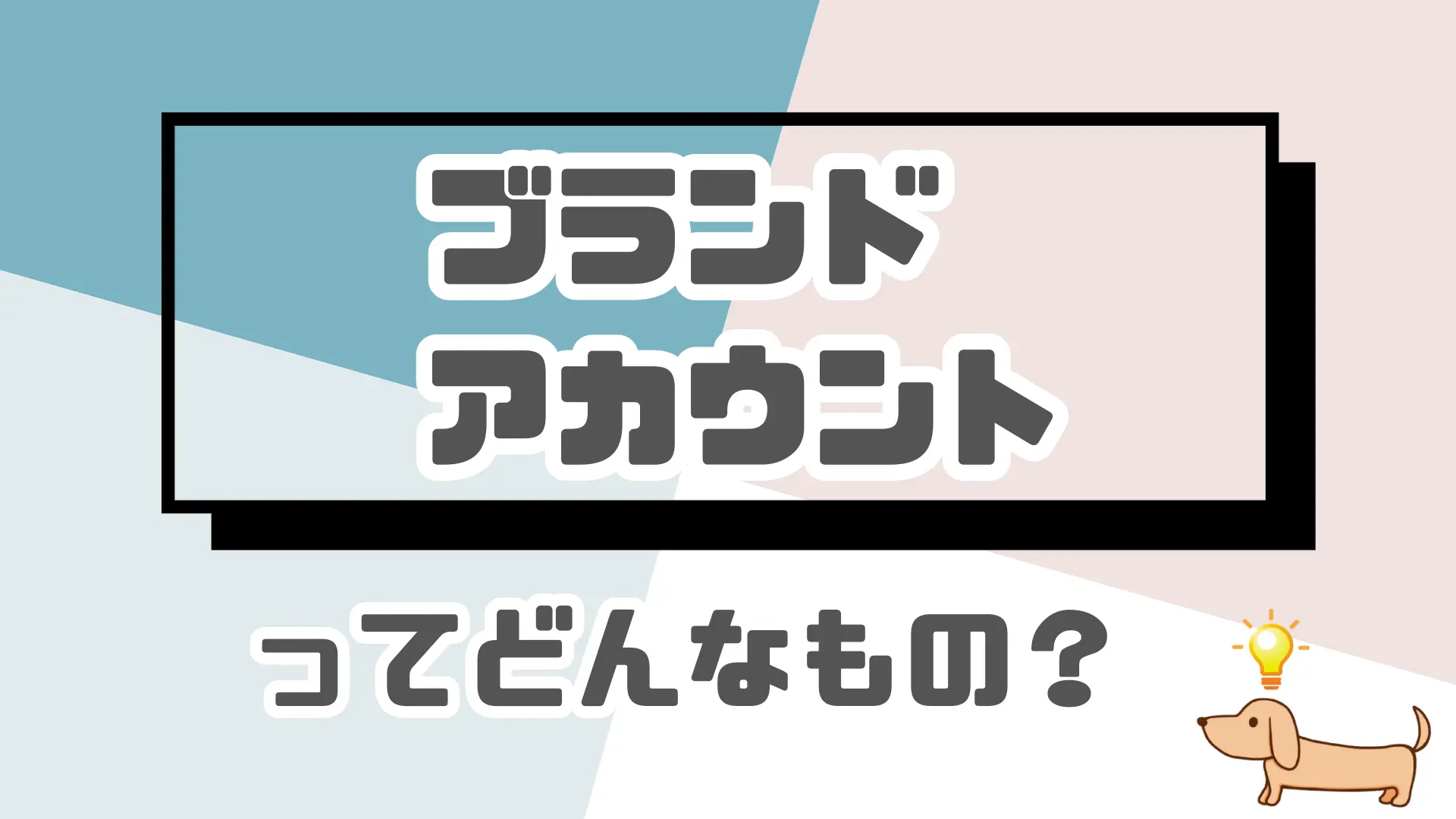副業を営んでいる方の中には
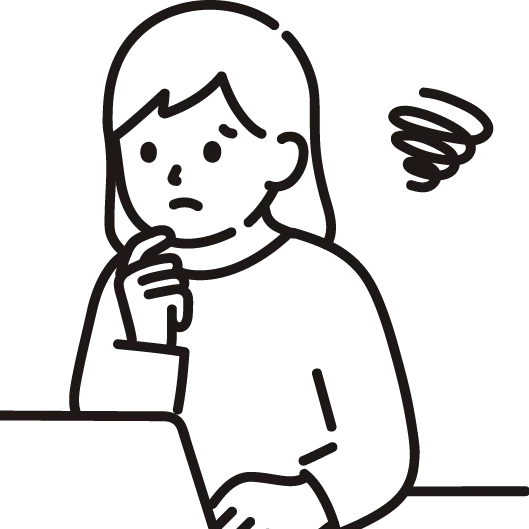
インボイスを受け取ったけどどうしたらいいの?
という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、副業を始めるにあたって知っておくべき「インボイス制度」について紹介していきます。
インボイスってそもそもなんなの?
自分に関係ある?
という方には必見の内容となっておりますので、是非最後までご覧ください。
まずは「インボイス制度」とはなにか、について簡単に説明します!
この記事の信頼性



10年以上いろいろなビジネスの財務コンサルタントをしてきた経験から、様々なビジネスの「仕組み」について解説します
インボイス(適格請求書)制度とは
インボイス制度とは、普段の業務を行う上で取引先とやり取りする請求書の書式(区分記載請求書等)を、インボイス制度に倣った以下のような書式(適格請求書等)に変更にすることです。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 税率ごとに区分して合計した対価の適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等



具体的にはこんな感じだよ
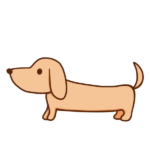
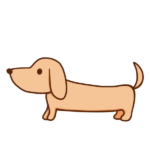
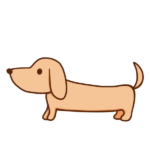
赤で囲まれた部分が重要っぽい
登録番号は、法人であれば「T+13桁の法人番号」、個人事業主であれば「T+13桁の数字」となっています。
当然ですが、事業主ごとの登録番号はいずれも重複しません。
インボイス制度と消費税の仕組みについてより詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。
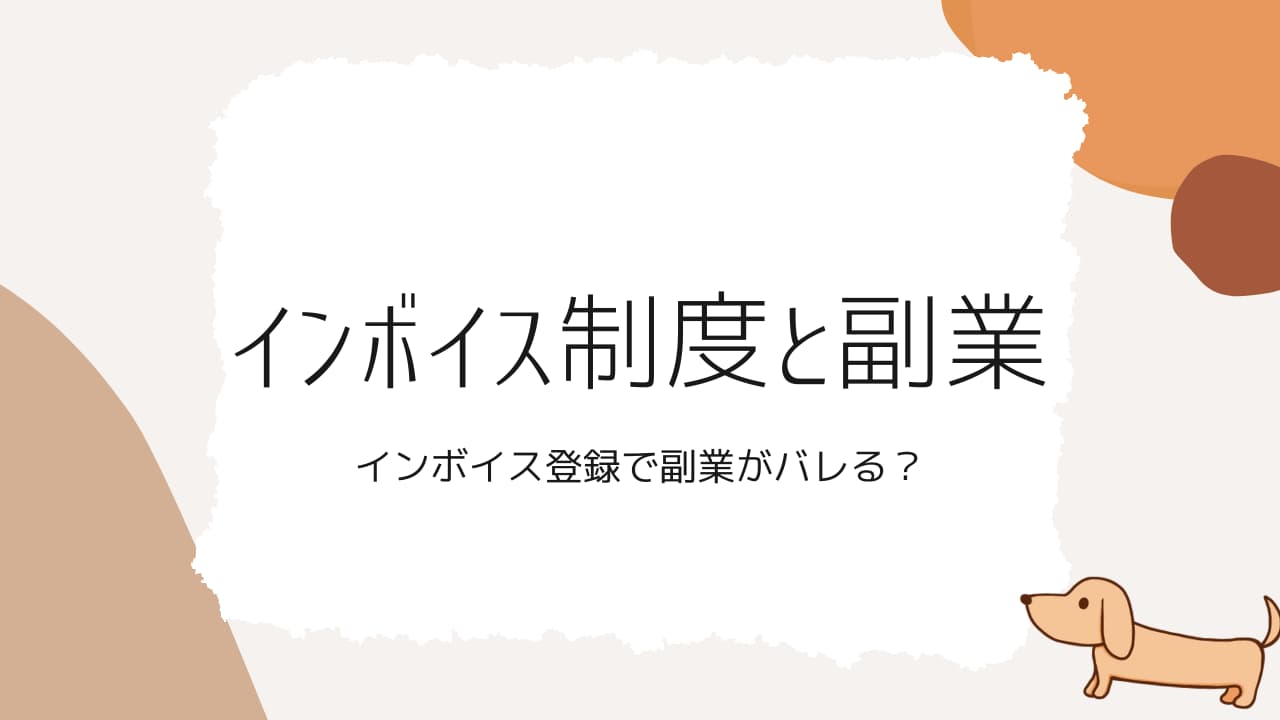
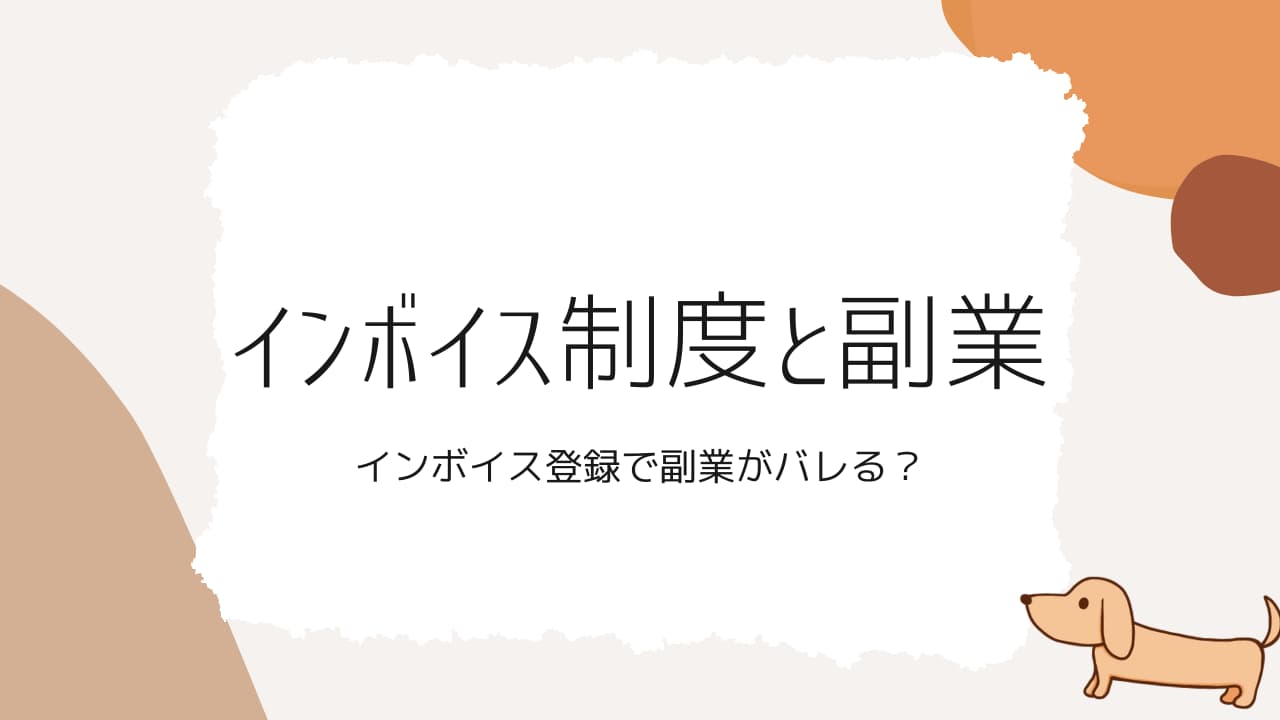
インボイスの判定をしなくてよいケース


副業を行っていて、インボイスを受け取る場面とは例えばこんな場合です。
- 業務委託の外注先に料金を支払う時
- 卸売業者から商品を仕入れた時
- 副業場所の家賃や光熱費を支払う時
業務委託契約の副業を自分一人で行っている場合は、経費自体がほとんどかからないのでインボイスを意識することは少ないでしょう。
しかし、何か経費を支払う場合にはその請求書がインボイスかどうかで納付する消費税が変わることがあります。
なぜなら一部例外を除いて、請求書がインボイスではない場合、支払った経費の消費税が0として認識されるケースがあるからです。



つまり、消費税を余分に払うことになるってことね
では、すべての事業者がみんな請求書がインボイスかどうかをチェックする必要があるのかと言えば、それも違います。
ここではまず「請求書がインボイスかどうか考えなくていい人」の例を3つ紹介します。
インボイス登録をせずに免税事業者を続ける場合
免税事業者である場合、消費税の納付義務がないため消費税計算の必要がありません。
つまりあなたが払った経費が消費税がかかっている取引なのかそうでないのか、ということすら認識する必要がないということになります。
この「消費税がかかっている取引なのかどうか」がまさにインボイスの判定をするということなので、免税事業者の場合は受け取った請求書がインボイスかどうかは考える必要がありません。
インボイス登録により課税事業者となった場合
インボイス制度の開始を機に、新たに免税事業者から課税事業者になった人も基本的にはインボイスの判定が必要ありません。
なぜなら、インボイス制度の経過措置として新たに課税事業者になった人には2割特例が適用されるからです。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合に税負担を「売上税額×20%」に軽減できる措置。申告に適用を申告するのみでよく、事前の届出が不要。



たとえば、売上100万円(税額10万円の場合、消費税の納税額は「10万円×20%=2万円」になるよ
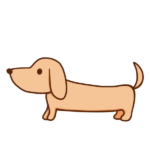
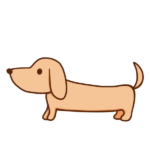
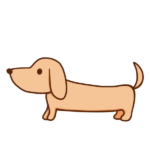
経費額に関わらず売上税額の8割を控除できる特例ってことか
もちろん利益率が20%以下の事業で課税仕入取引が9割というケースであれば、8割を超える仕入税額控除(支払った消費税額)となるので、一つ一つの取引がインボイスかどうか判定した方が消費税が得になるケースもあります。
しかし、あくまで「副業」であるという事を考えるとかなりレアケースでしょう。
また、2割特例は令和8年9月末までの時限立法であるという点にも注意が必要です。
簡易課税事業者である場合
簡易課税事業者における消費税計算の仕入税額控除額は「みなし仕入れ率」として業種ごとに一律に決まっています。
年間売上高が5000万円以下の中小事業者が対象となる消費税の簡易的な計算方式。消費税額は「預かった消費税額×みなし仕入れ率(業種ごとに定められた割合みなし仕入率)」で計算される。
つまり、あなたが経費をいくら払おうが「支払った消費税額」は売上額によって決定されますので、受け取った請求書がインボイスかどうかの判定が必要ありません。



ちなみに2割特例と簡易課税事業者は併用可能で、申告時に有利な方を選択できるよ
簡易課税のみなし仕入れ率
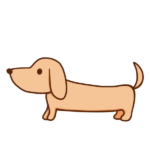
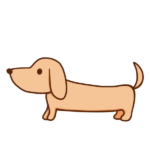
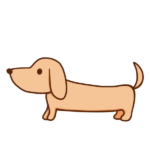
「業種ごとに定められた割合」ってことは、業種ごとに納付消費税額に有利不利があるのか



具体的なみなし仕入れ率は以下の通りだよ
| 事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 |
| 第2種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。 |
| 第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 |
| 第4種事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。 |
| 第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。 |
| 第6種事業 | 40% | 不動産業 |
インボイスの判定が必要なケース


反対に、インボイスの判定が必要となるケースは、インボイス以前から本則課税の課税事業者であった場合です。
一つ一つの取引について消費税がかかわる取引かを判定し、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて消費税計算を行う方式。
この場合、消費税計算を行うにあたって「支払った経費が消費税のかかわる取引かどうか」は納付する消費税額に直接影響しますので、一つ一つの取引についてインボイスの要件を満たしているかどうかの判定が必要です。
受け取ったインボイスの管理方法


取引先は通常一つだけというケースは少ないでしょう。
数か所~数十か所の取引先から請求書をもらうケースが一般的です。
そういった場合、まずは全ての取引について以下の情報をまとめてリスト化するのがおすすめです。
- 取引先名
- インボイス登録の有無
- インボイスの書式
「インボイスの書式」とは、その取引先が「どの書式をインボイスとしているか」ということです。
具体的には、「請求書」、「納品書」、「領収書」などが挙げられます。



納品書だけがインボイスで請求書は違うってパターンあるの?



全然あるし、その逆もあるよ
インボイスの特性として、『1インボイスにつき、税率ごとに端数処理を1回』行うというものがあります。
例えば、納品書で消費税計算を行った後に、同じ取引が記載された請求書上で再度消費税計算を行うことはできません。
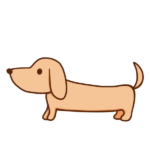
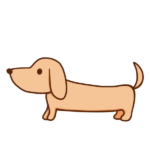
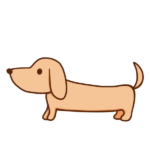
一つの商品毎じゃなく、一つのインボイスごとに端数処理が1回ってところがミソだね



なので納品書をインボイスにして消費税計算を行っている場合は、請求書はインボイスの内容をまとめたメモ紙みたいな扱いになるよ
つまり「どちらもインボイス」という状況は生まれませんので、事前に取引先に確認しておくのがよいでしょう。
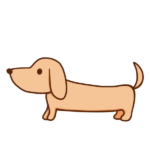
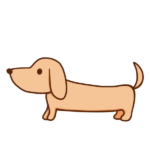
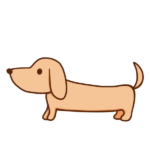
じゃあ最初に全部聞いてリストにしておけば安心だね



途中で登録を解除するケースもないことはないから一応毎回インボイスかどうかの判定は必要…というのが原則だけど、実務上では一度確認したらそこまで厳密には皆チェックしないと思う…
インボイスを受け取った後の会計処理
インボイスの判定が終わったら、後は「インボイス登録の有無」に区別して会計処理を行いましょう。
その際、インボイス未登録者からの仕入は登録者と比べて明確になるように、新しい区分コードを設定するなど集計
できる管理体制を予め決めておく必要があります。
- インボイス制度に則っている請求書:通常の課税仕入取引
- インボイス制度に則っていない請求書:8割控除の新しい区分取引(2割特例適用期間)
また、会計処理を行うソフトとしては、買い切りのものよりもクラウドベースのものの方がおすすめです。
理由は、複数の端末で利用できることと毎年の税制改正にリアルタイムに対応してくれるからです。
複数端末の便利さとは、例えばスマホで業績をタイムリーにチェックできたり、スマホで撮った領収書の写真を仕訳に取り込んだりと効率的な運用ができることです。
また、税法は毎年変更があり、税率や税額計算方法など大きな変更も少なくありません。
特にインボイスや電子帳簿保存法などこれから施行される制度については定期的に扱いが変更となる可能性があります。
クラウドベースのソフトだとアップデートが自動でかかる為、何もせずに常に適正な状態で税金計算が可能です。
一方買い切りソフトの場合は、大きな変更があった都度その制度を読み解き、手動で初期設定を変える必要があるので、結局はクラウド会計ソフトの方が実用的という面があります。
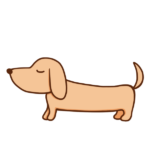
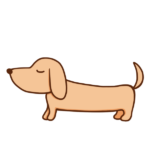
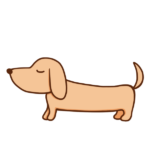
会計ソフトか…Excel管理じゃダメ?



所得税だけの確定申告ならそれでもよかったかもしれないけど、インボイス施行後は面倒が増えると思うなあ…
仮にあなたの事業がまだ始めたばかりの段階で、
- 請求書の書式は簡易なもの
- 日々の帳簿もExcelや手書き
- 取引先の数も毎月ほぼ一定
- インボイス登録はせず免税事業者を貫く
というのであればExcel管理でもある意味十分でしょう。
ただ、今後も事業を拡大する予定がある人や、消費税計算を行う必要がある人は絶対に会計ソフトを使うことをおすすめします。



会計ソフトなら取引ごとの消費税計算はもちろん、申告書の作成までほぼ自動でできるから楽だよ
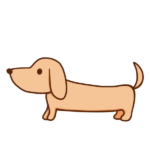
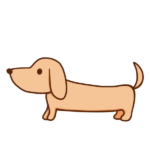
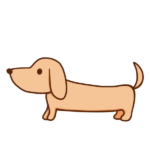
逆に自動じゃなきゃ全く計算なんてできない自信がある
以下の会計ソフトには消費税計算から申告書の作成まで一通りの機能がついているのでおすすめです。
会計ソフト導入に対する補助金
さらに、インボイス制度開始に併せて会計ソフトの導入を行う場合、経済産業省の「IT導入補助金」が利用できます。
IT導入補助金は、経済産業省、中小企業庁、中小機構が提供する中小企業向けの制度で、ITツールの導入に関する費用の一部を補助するものです。
「IT導入補助金」を利用して、インボイス制度導入のための会計ソフトを購入する際、最大450万円までの半額分の補助を受けられます。
また、買い切りのソフトではなくクラウド利用のソフトを導入した場合には、最大2年間の利用料が補助の対象となります。
インボイス登録についてよくある質問





この記事に関してよくある質問をいくつか紹介します
まとめ
- インボイスは消費税計算に関わる制度
- インボイスかどうかの判定は本則課税の課税事業者のみ必要
- 全ての取引先についてインボイス登録の有無のリストを作った方が良い
- インボイス施行後は会計ソフトの導入も検討しよう
ここまでインボイス制度と受け取ったインボイスの取り扱いについてお話ししてきました。
インボイスの有無を正確に把握せずに消費税計算を行った場合、消費税を少なく申告しまう可能性があります。
当然ながら、少なく申告することは脱税行為になりますので、重加算税や不納付加算税が課されるケースも考えられます。
インボイス取り扱いについて正確に理解し、事業に余計なリスクを生まないように気をつけましょう。



ここまでお付き合いいただきありがとうございました